退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
- POINT
-
- 一定の条件を満たしていれば、引き続き当組合に加入できるしくみがあります。
- 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。
退職して被保険者の資格を失ったときは、健康保険組合から交付された有効期間内の各証(資格確認書等)を5日以内に返納する必要があります。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。
※マイナ保険証に最新の資格情報が表示されない場合は、加入中の保険者へご確認ください。
退職後に加入する医療保険(図1)
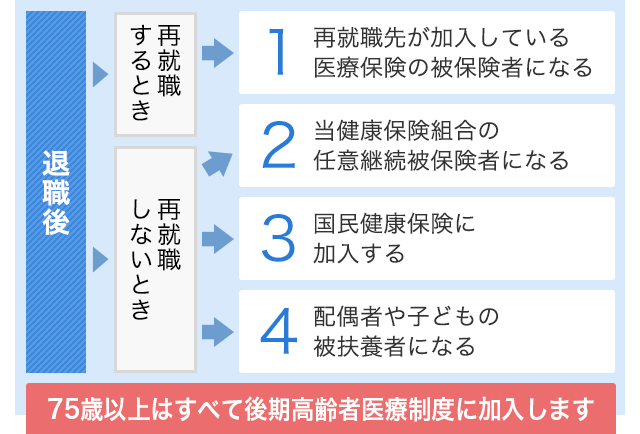
- ※倒産・解雇などにより離職された方(雇用保険の特定受給資格者)及び雇止めなどにより離職された方(雇用保険の特定理由離職者)の国民健康保険(税)を軽減する制度(以下「軽減制度」という。)が各市区町村で平成22年4月1日より開始されました。
この制度においては、特定受給資格者等の国民健康保険料(税)について、離職の翌日からその翌年度末までの間、前年所得の給与所得を100分の30として算定することから、失業後、当健保組合の任意継続被保険者となった場合よりも納めるべき保険料が低くなることがあります。双方の保険料等を比較してどちらに加入するかご検討ください。
尚、国民健康保険の保険料の額や軽減制度に関するお問い合わせは、お住まいの市区町村の役所へご相談ください。
- 参考リンク
-
- 特定受給資格者の範囲の概要(厚生労働省ホームページ)
引き続き当組合に加入する場合
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。
任意継続被保険者となれる人
次の全ての要件を満たしていることが必要です。
- 退職などにより健康保険の被保険者資格を失った方
- 資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
- 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること
任意継続被保険者でいられる期間
任意継続被保険者となった日から最長2年間です。
※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。
負担する保険料
被保険者の自己負担分と事業主負担分をあわせた全額を自己負担します。任意継続被保険者になると、事業主による保険料負担はありません。毎月10日までに自分で保険料を納付します。
保険料の納付方法は月払いのほか、一定期間の保険料を一括して納付する前納があり、前納の場合は法定の割引が適用されます。
前納できる期間は半年毎(4月~9月分、10月~翌年3月分)、または1年毎(4月~翌年3月分)です。
詳しくは健康保険組合にお問い合わせください。
標準報酬月額
保険料計算の基礎となる標準報酬は、①資格喪失時の標準報酬月額か、②前年9月末日現在の当健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額を比較して、①と②いずれか低い額に決められます。
- ※健康保険組合が規約で定めた場合は、②より①が高い場合でも、①の標準報酬月額を算定の基礎とすることができます。
- ※保険料額は、保険料率の変更、平均標準報酬月額の変更、介護保険該当・不該当によっての変更はありますが、現在の収入の増減による変動はなく、扶養家族の人数にかかわりなく2年間同じ金額となります。
保険料の納付方法
初回月の保険料納付後は、その月の10 日までに納付します。10 日までに納付がなかった場合、保険の資格が自動的になくなりますのでご注意ください。
振込手数料はご本人負担となりますのでご了承ください。
- ①納付書を利用した銀行(全金融機関※)窓口からの振込
(※ゆうちょ銀行、滋賀銀行、三井住友銀行を除く。ATM、インターネットバンキングからの振込は可能)
納付書(領収書等付4 連ミシン目入り)をご利用いただき、銀行窓口よりお振込みください。直接、当組合経理課窓口に納付書をお持ちいただき、現金でのお支払いも可能です。
期限当日の振込は翌営業日扱いとなる場合がございますのでお早めにお手続きください。
期限翌日以降の着金はこちらから確認のご連絡がいくことがあります。
- ②郵便局から現金書留での納付
現金書留に該当月の納付書と保険料を同封して当組合適用課宛にお送りください。
(期限必着になりますのでご注意ください)
- ③銀行ATM またはインターネットバンキングからの振込 ※領収書は発行されません
指定の口座へお振込みください。(納付額、納付期限は納付書をご確認ください)
※指定口座は納付書に記載がございます。どちらの口座でも構いません。
必ず振込人の欄に納付書上部の番号(保険証の番号:記号9900 に続く5桁の番号)と被保険者名を入れてください。
(期限翌日以降の着金は認められませんのでお早めにお手続きください)
※保険料の誤振込の事例が発生しているため、税公金・振込自動受付機(STM)は使用しないでください。
保険給付の内容
出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。
※資格喪失後の給付に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給されます。詳しくはこちらを参照ください。
任意継続被保険者の資格を失うとき
次の事由に該当した場合は、該当するに至った日の翌日(4、5の場合はその日)に任意継続被保険者の資格を失います。
- 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
- 死亡したとき
- 保険料を指定された納付期日までに納めないとき
- 再就職して、他の健康保険などの被保険者となったとき
- 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
- 任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき
備考
- 就職して任意継続保険をやめたい
就職先の保険証ができたら当組合の適用課にご連絡ください。 - 住所または氏名が変わった・被保険者本人が亡くなった
直ちに当組合の適用課にご連絡ください。 - 任意継続の期間が終了した場合
期間満了日(保険証に印字されている喪失予定日)の1週間位前に「資格喪失予告通知書」および「喪失証明書」を送付しますので、国民健康保険に加入する時はその喪失証明書を市(区)役所などにご持参して保険の切り替え手続きをしてください。 - 軽減制度に該当する方で国民健康保険に加入を希望する場合
当組合の適用課までご連絡ください。
退職した後も給付を受けられます
退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。
この場合は任意継続被保険者となっていない場合も受けられます。
退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)
| 支給の条件 | 退職時に傷病手当金を受給中または受給要件を満たしていて、引きつづきその病気やけがの療養のために働けない場合 |
|---|---|
| 支給される期間 | 傷病手当金の支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月間
|
- 参考リンク
| 支給の条件 | 退職時に出産手当金を受給中または受給要件を満たしている場合 |
|---|---|
| 支給される期間 | 出産手当金の受給期間満了まで |
- 参考リンク
| 支給の条件 | 資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合 |
|---|
- 参考リンク
| 支給の条件 | (1)資格喪失後3ヵ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし) (2)傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間 (3)これらの給付打ち切り後3ヵ月以内に死亡した場合 |
|---|
- 参考リンク
自己都合で退職したとき
自己都合退職で、失業給付を受給するまでの待期期間・給付制限期間中は、被保険者により生計維持されている場合は、扶養申請が可能です。
ただし、受給金額が扶養基準額(※)を超える場合は、後日、受給開始日にて被扶養者資格削除手続きが必要です。
扶養基準額を超えているにもかかわらず、そのまま当健保組合の保険証を使用した場合は、医療費の返還請求をいたします。
- ※扶養基準額とは、基本手当日額3,612円未満(60歳以上は5,000円未満)で、かつ基本手当日額に360日を掛けた額が被保険者の年収の1/2未満です。
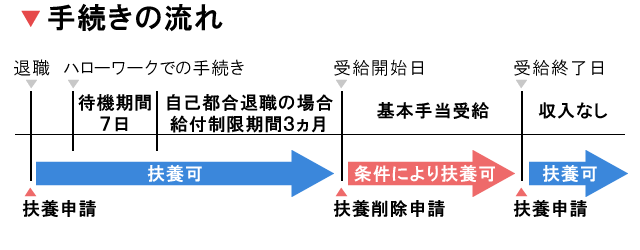
退職した後の健康診断
図1の2を選んで任意継続被保険者になった場合は、今まで通り健診を受けていただけます(在職中も含めて年度(4月~3月)で1回受けられます)。
また、組合健康管理センターでは、国民健康保険加入の方や75歳になって後期高齢者医療制度に加入した方も全額自己負担で今まで通りの健診を受けていただけます。日程等の詳細は、健康管理課までお問い合わせください。
TEL:03-3661-2257
| 人間ドック | バリウム35,000円 |
|---|---|
| 胃カメラ40,000円 | |
| 若年層健診 入社健診 |
10,000円 |
- 参考リンク






